君は飛火野耀(とびひの あきら)を知っているか 第7回『神様が降りてくる夏』
さて、「君は飛火野耀を知っているか」第7回はいよいよ氏の最後の発表作品『神様が降りてくる夏』を紹介します。

この作品は1996年にメディアワークスから発行された、飛火野耀氏唯一の単行本作品、そして氏の発表した最後の作品となります。
当時あまり出回らなかったのか、今となってはなかなかの希少本、このブログを書くに至っても図書館からの借本でどうにか読了することが出来ました。

この作品で描かれているのは“人間の理解を超えていて、人間の言葉では名づけることが出来ないもの”。
そして、“それを前にしたとき、あるものは神とあがめ、またあるものはそれを悪魔のように忌み嫌ってきた”何かというもの。
氏はたびたびこうした題材を物語の奥底に据えた世界観を描いてきましたが、今回の作品はまさにそれらの集大成。
早速その読みどころをご紹介したいと思います。
1.謎へと突進するカリカチュア
本作では、先に説明したような「人智を超えた何者か」をめぐって、様々な人物が登場します。
ジャーナリスト、漫画家、小説家、新興宗教の教祖、カルト集団の預言者、芸術家、女子高生(中退)、大学生等々、立場も年齢も多種多様、それぞれの違いによってみんな違った考え、違ったものの見方を持っています。

そして、その「何か」に対する感じ方もみな、ばらばら。
あるものはそうした感受性を日常生活への支障と考え忌み嫌い、またあるものは強い感受性をして「自分を選ばれし者だ」とし権力を求める、そうか思えばまったく感受性がなく理屈で捉えようとするものもあれば、それら全体を平凡に見つめる視点もある。
そして物語は一部の人々によって予兆されたある時、ある場所へと集約されてゆき、それに伴って人々の考えや行動もエスカレートし、てんやわんやの様相を示してゆく。
全く正体が分からないものに右往左往する群像劇はどこか滑稽なカリカチュア。
時にシリアスに、時にユーモラスに、波乱を帯びながらミステリアスな一点へと突き進む展開は最後まで一気に読み進めてしまいます。

2.あまりにも魅力的な「トビヒノ氏」
飛火野耀氏はこれまでの作品でも度々自身のアバターを登場させていますが、本作でもほとんどメインキャラの一人として「トビヒノ氏」が大いに活躍してくれます。
そもそも『飛火野耀』という小説家自体が覆面作家であり、造形されたパーソナリティであるので、本作に登場する「トビヒノ氏」は二重の造形を経ているということになります(ややこしい)。
あごひげとメガネが特徴的なしがない三文小説家。雷と電話が嫌いでボロアパートに一人で住んでる中年男性。博識で映画に音楽に深い造詣を持っており、理屈屋でなんとなく人生が不器用。
まさに、これまでのプロフィールに書かれているまんまの人物像。

彼の一挙手一投足、彼の言葉のひとつひとつに、幻の作家、飛火野耀氏の思いがまんま投影されているようで、実に興味深いものがあります。
なにしろ現実にはその姿がほとんど晒されていない小説家。氏の作品の愛好家としては愛着を覚えずにはいられません。

3.示される怒涛の“飛火野イズム”
物語は最終的にある時、ある場所においてその「何か」との遭遇を果たすのですが、そこに描かれるものは実に凄まじい現象。
といっても基本的にその「何か」は人の知覚を超えているので、登場人物ほぼ全員が「何が起こったのかよく分からないが、何か凄いものが通り過ぎたらしい」といった感覚に集約します。
ただその中でもどういうわけかもっともそれらから心理的に縁遠く、どちらかというと巻き込まれるだけだった大学生が、一番強烈にその引力に引っ張られるのです。
彼は突然強意識が解放され、ありとあらゆる物事が一点の曇りもなく明らかになり、さらには地球上のすべての知識が一挙に押し寄せてくるという現象にさらされます。
情報の洪水に怯えた彼は意識をとざしてしまい、結局何事もなかったようになるのですが、ただその一瞬に垣間見られる世界観は圧倒的。

それは、我々の世界から一つ上の階層にシフトした客観的視点とでもいうようなもので、まるで人間が知覚することが出来る全世界が、さらに大きな構成体の一つに過ぎないとでもいうような概念であり、同時に我々一個一個の意識もまた、大きな構成体という概念の中では一つにまとまって結合しているとでもいうような凄まじいことわり。
氏はこれまでの作品でも度々こうした世界観を作品に描いてきました。
例えば「もう一つの夏」でのサイバースペース深部、または「UFOと猫とゲームの規則」における世界説明等々。
そうした“飛火野イズム”とでもいうような概念の中でも、本作に描かれるのは正にその極致。
その筆述にもどこか神がかったようなものがあり、まるで小説家・飛火野耀氏が小説という媒体を通して伝えたかった全て解き放ったかのような迫力が感じられます。
しかし、ここで思いの丈を全て出し尽くしてしまったのか、本作を最後に氏の名前は文壇から一切姿を消してしまうのです。

まとめ
飛火野耀氏が小説界に放った最後の一閃、『神様が降りてきた夏』。
そこには飛火野耀氏による“飛火野イズム”がなみなみと溢れているかのようです。

文中、小説家・トビヒノ氏はこんな事をつぶやきます。
「…つまりだね、政治にしろ宗教にしろ、二つの集団がたがいに自分たちが正しいとして争っているとき、一方が絶対に正しいなんてことはありえないってことさ…(中略)…ところが、今でも自分たちこそが正義だと主張する連中が後から後から出てくるのには、本当に困ったものだ…そういう奴らが、この世界を破滅させちまうんだ…。」
飛火野耀氏が、その人生でいったい何を見、どういう時代を生き抜いてのかは全く定かではありません。
ただ、氏の作品にはいずれも、イデオロギーが支配を求めるところを嫌悪する傾向が感じられます。
特にこの作品が発表されたのはあの宗教団体の無差別テロ事件の余波が残っていた時代でした。
またそうでなくとも、世界全体は常にある種の強烈な思想観念によって歪み、引き裂かれ、絶え間なく綻び、そして修復を繰り返しています。
飛火野耀氏が『小説』という媒体を通じて我々に伝えたかったメッセージ。
それは、イデオロギーが征服を欲するところがなく、人々が互いに心と心を通い合わせながら発展をとげてゆく、豊かな社会への願いであったのかもしれません。

◇神様が降りてくる夏
◇飛火野耀(著)
◇1996年
◇メディアワークス
◇AMAZONリンク
さて、次回、『君は飛火野耀(とびひの あきら)を知っているか』最終回は総括的に綴って締めくくりたいと思います。

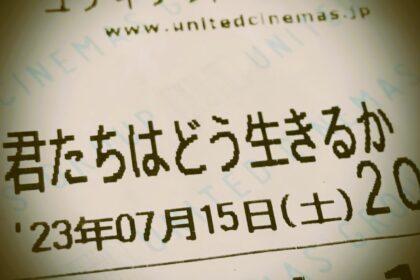




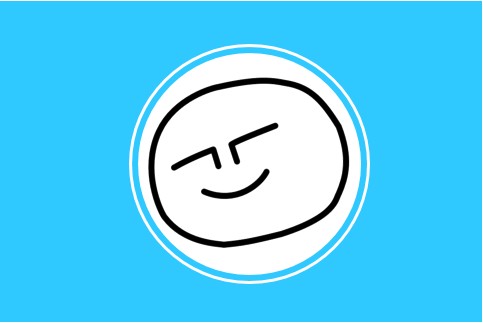




コメントを残す